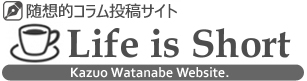先日、某有名人がTwitterで、ある団体に対して批判の発言を行ったのをニュース記事で見ました。私が注目したのは、この発言の内容よりも言い方です。その有名人の方は「○○は、○○しろよ」という言い方で発言を行っていました。
指摘・注意、そして批判といった発言は、「~しろ」とか「~というのはおかしくないか?」など、命令口調か批判口調で行われることが多くあります。こうした発言の中には、正論も多くあるかもしれません。(実際、「その通りだと思います!」とか「良く言ってくれました!」など、賛同する声が多く寄せられる場合も多くあります)
ですが、このような言い方では、言われた当事者は自分のプライドを守ろうと防戦したくなるのが普通です。もし、間違いであることを認めざるを得ない状況であっても、素直に認める気持ちにはなりません。多くの人の目に留まる場で恥をかかされ、晒し者にされたと恨みや怒りの感情を持つことの方が多いでしょう。
ネット上では、ニュース記事のコメント欄、SNS、掲示板などで気軽にコメントを発信できます。他人の発言を見たり、見知らぬ人と意見交換ができるというのは便利で楽しい面も多いですが、一方で自分が正しいという理由で相手の自尊心を傷つける物言いや攻撃するような発言が日常的に行われています。言い争いにまで発展すば、お互いが攻撃し合う勝ち負けのゲームと化し、もはやキッカケとなったことなどどうでもよくなります。
ネット上の事に限らず、実生活(学校、職場、家庭など)でも相手の尊厳を傷つけるような言い方をする場面では、大抵は自分が正しく、相手が間違えているという正当性を前面に出して行われることが多いものです。その態度は、まるで自分が正義で「自分は悪を許さない人間なのだ」と主張しているようにさえ見えます。
そこで疑問に思うことが、そもそも正しければ言い方はキツくてもよいのか?相手の自尊心を傷つけてもよいのか?そういった発言をすることは、目的からすれば合理的なのか?ということです。
例えば、身体的な暴力は悪いこととして許されないことは誰でも知っていますが、一方的に不当な暴力を受け、反撃しなければ自分の身が危険に晒されるという緊急事態においてのみ、許されます。これを「正当防衛」と言います。「不当な攻撃から身を守る」という前提であれば、誰も納得できることです。しかし、正しければ相手の尊厳を傷つけるような物言いをすることは、正当な状況であるとは言えません。
では、合理的な面ではどうでしょうか。指摘・注意・批判をすることは、相手に自分の意見を受け入れさせることです。しかし、ネガティブ感情を向けられて命令口調などで言われれば、相手は自尊心を守ろうと構えます。言い方が良ければ快く受け入れたかもしれないことが、逆に意固地になって反抗するかもしれません。もし、関係上の立場が弱く、従わざるを得ないとしたら、意見には従っても内心、反感を持たれ、恨みを買い、関係も悪化します。反省して素直に意見を受け入れようなどと思う人はほとんどいません。つまり、合理的な意味もないということになります。
こう考えると、言っていることが例え正しくとも、相手の尊厳を傷つけるような物言いをすることに正当性も無ければ合理的に考えても良い結果になるわけではなさそうです。
しかし、まるで正しければ、正当防衛のように相手の尊厳を傷つけても構わないと法律で定められているかのようにそのような行為をする人が世の中には圧倒的に多いのが実情です。
多くの場合は、心の中に発生した不条理や自分の思い通りにならない不満などのストレス感情を吐き出したいという衝動と、自分の思い通りにしたいというエゴの欲求だけなのです。そのためにもっともらしい理由を付けて、自分の行為を正当化するのです。
自分の中の不満感情を進んで抑え、態度や言動などをコントロールしようとするのには、まずそういったことに価値感を持たなければなりません。そうでなければ、そもそも発散したい不満感情を抑えるような動機が生まれないからです。この価値感は人間として高尚なものです。
果たして、世の中にそのような価値感を持っている人がどれくらいいるでしょうか?それは、「そもそも正しければ相手を攻撃をしても構わないということがおかしい」と疑問すら抱かない人が大半だという事実を見れば分かります。
こういった話しを読んで、一人でも多く理想的な価値感を持つことを考える機会となればと思います。