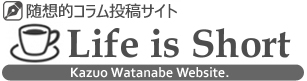人生は理不尽なことに満ちている
人生においては、「なぜこんなことが起こるのか」「なぜこんな目に遭うのか」「どう考えても間違えている」としか思えないような解せないことが起こります。
幼い子供の頃には皆、おとぎ話や童話を読み聞かせられます。数ある童話の中でも、私が強く印象に残っている物語の一つに、グリム童話の『ブレーメンの音楽隊』があります。年老いて用済みになったと飼い主に扱われたロバが音楽隊に入るためにブレーメンを目指して旅に出て、その道中で同じように不幸な境遇にある犬、猫、鶏を仲間にし、最後はみんなで協力して泥棒を撃退し、その家にいつまでも仲良く暮らすという話しでした。(今思い返すと、「ブレーメンに行く目的はどうしたんだ!」と思いますが)
この物語は、不幸な境遇にあった者が困難を乗り越えて最後は幸せに暮らす、泥棒(悪い者)は成敗されるという「道理」が成立しています。小さい子供には、このように道理が成り立つことを教えるのが正しいことです。一部の例外はあっても童話は凡そ、正義が勝ち、ハッピーエンドで終わる話しが多いものです。
小学校低学年の頃、特撮ヒーローの「ウルトラマン」が好きで、学校から帰ってくると夕方からやっていた再放送をテレビにかじりついて観ていました。ウルトラマンは、地球を破壊しようとする怪獣や侵略してくる星人(宇宙人)を毎回、倒します。その強い姿に憧れました。
しかし、ウルトラマンは最終回に強敵に負けてしまいます。最後は、地球防衛軍(科学特捜隊)がウルトラマンを倒した敵を新兵器で倒します。おそらく、製作側の意図としては、「これからは地球は地球人の手で守る」ということではないかと思います。ウルトラマンは故郷の星から来た仲間から命を貰い、最後は自分の星に帰ります。物語としては、ちゃんと悪が敗れ、正義が勝った結末なのですが、「強いウルトラマンが負けた」ことがショックであり、「強いウルトラマン」であり続けて欲しかった私は、それがずっと納得いかず、心に引っ掛かっていました。
同じく小学生の頃、私の家の近くに民宿旅館があり、そこの飼い猫が毎日、私の家に遊びに来ていました。よく私に懐いてくれて、私もその猫が大好きで、私にとっては良い友達でした。私の実家は食品店を営んでいて、その猫は朝、店が開店したら来て、夜に閉店したら帰るという生活をしていました。
ある日、学校から帰ってきた私をショックな知らせが待っていました。その猫が朝、ウチへ来る途中、車に撥ねられて死んでしまったと聞かされたのです。大きな悲しみに見舞われ、立ち直るのにかなり時間を要しました。「なぜあんなに仲が良かったのに、お互いが好きだったのに、別れなければならないのか?」と自問自答した記憶があります。(ペットとの別れは、子供の頃に多くの人が経験することだと思います)
このように、強いヒーローが負ける、大好きだった猫と突然死別するといったことで、徐々に「常に正義が勝つわけではない」「童話のように”いつまでも仲良く暮らしましたとさ”とはならないことがある」そして、「生きていると理不尽なことが起こりえる」「人生は時に耐えるしかないことが起こる」ということを、子供ながらに徐々に学んだ気がします。
生きていく上では理不尽耐性が必要
道理からすれば、正しいこと・良いこと・美しいことが「勝つ」べきであるし、そうあるようにしていくのが人として正しい道です。「正直者がバカを見る」という言葉がありますが、正直者が損をし、嘘つきが得をするの本来、道理からすればあってはならないことです。ですが、残念ながら世の中は不条理なことに溢れています。
「あんな酷い奴が大金を得て悠々自適に生きしてるのに、一方でこんなにいい人が不幸な目に遭って辛い人生を生きている」そういう例も世の中には多いものです。日々、新聞やテレビやネットのニュースを見ていても理不尽だ、不条理だと感じてしまうようなニュースが珍しくありません。そうではないでしょうか。
神がいれば、道理に従って善行を行った者や正直者には褒美を、その逆の者には罰を与えるはずですが、実際には正直者の身にも罰としか思えないようなことが起こります。これが現実です。現実には神も仏も存在しないのです。(私が実質的な無宗教者であるからこのような無責任なことが言えるのですが、日本ではそのような人が多いと思います)現実の世界は、おとぎ話や童話とは違い、悪が勝って終わってしまうことも多々あると痛感します。
では、理不尽な出来事に遭遇したとき、どのような心的態度を取るべきでしょうか。理不尽なことが自分の身に降りかかると、ネガティブな感情が湧き上がるものです。それでも自暴自棄になったり、怒りの感情を表出させても余計に事態が悪くなるだけです。その気持ちは充分に分かります。時には悲しみや怒りを抑えるのが非常に困難なこともあるでしょう。ですが、理不尽な出来事があり、それに耐えなければならないというのは、生きていくからには絶対に避けられない条件なのです。「なぜ自分だけこんな目に」と思いがちですが、皆そう思っています。だからこそ、「理不尽耐性」を付ける必要があるのです。
「理不尽耐性」が低い人は、不満の感情を抑制できず、露骨に不機嫌になったり、気分が悪いままの状態が長く続きます。そして、抑制できない人に限って、実は理不尽なことではなく自業自得なことであったり、自分の思い通りにいかないというわがままな不満を勝手に理不尽だと思い込んでいる場合も多いものです。理不尽だと思っていたが、実は因果応報ではなかったか?自業自得ではなかったか?今回の件で今後の教訓にすることはないだろうか?対処は?予防は?そう冷静に考えることです。
一方で、周囲から見てどう考えても理不尽な目に遭い、気の毒としか思えないようなことがあっても感情や気分を乱すことなく落ち着いていられるように見える人も世の中にはいるものです。そのような人を見習うようにしましょう。
理想なのは、自分の道理に価値感を持つこと
そして、「理不尽耐性」をつける一番理想的な方法は、自分の中の価値感を人としての道理、「正しいこと」「良いこと」「美しいこと」つまり「真善美」を基準に判断し、行動する人間になっていくことです。
自分の中の価値感が常に真善美にあり、常に正直にそれに従って生きていれば、自分の中では理不尽なことや不条理は起こらない。自分の判断と行動の基準に価値があるわけですから、自分でコントロールできる範囲外で起きた偶発的な出来事や理不尽なことは、それはもう仕方ないことだと思える。それこそが大事なのです。
例えば、善行を行った結果、皮肉にも悪いことが起きたとします。普通だったら「善いことをしたのになぜこんな目に遭うんだ。全く理不尽だ」と思うでしょう。それは一見、正常な反応と思えますが、価値感が自分の中の真善美にあれば、善行を行ったことは道理にかなったことを実践したことであり、そこには理不尽なことなどないのです。
偶発的に起きた悪い出来事は無いに越したことはありませんが、それでやらなければよかったということにはなりません。それが自分の内面(価値感)に重点を置いて生きるということです。(もちろん、悪い結果に繋がってしまった場合には、充分に原因を考察して今後に生かす必要があります)
逆に、悪事を働いたのに良いことが起きたとします。結果的に良いことが起きても悪行を実践したのなら、それは人としての道理に反したことをしたので結果に関わらず、今後は行わないと反省すべきです。そのような価値感を持ってに生きていけるようになれば、自ずと「理不尽耐性」は身についていきます。
道理に反した出来事に耐え、自分の中の道理に価値を置いて生きる。これは「信念を持って生きる」ということであると言えます。