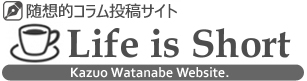子供の頃に、フランスの作家サン=テグジュペリの有名な著書「星の王子さま」を読みました。現在までその一度しか読んでいないので、内容もほぼ覚えていないのですが、物語の中に出てくるある言葉だけが強く記憶に残っています。それが、「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ。」というセリフです。子供心に、これは真実を的確についているという強い印象を受けました。それがこの言葉を今まで忘れていない理由だと思います。
確かに、「誠実」「勇気」「やさしさ」「謙虚」「思いやり」「貢献」といった、人の美しい行いが人生では大切であり、それらは目に見えるものではありません。人の行いや言動、またその行動の結果には、「正しい・誤り」「善い・悪い」「美しい・醜い」という意味が伴います。行動そのものは目に見えますが、それが何を意味するかは目に見えません。目に見えないし、数値で測定したりできないことだから、人の行いや行動の結果には様々な解釈や理解があるわけです。
しかし、多くの人は他人と意見が対立するとき、目に見えないということ、つまり確固たる証拠がないことを自分に都合よく利用します。自分の方が正しいという根拠は、「自分の意見こそが客観的事実」という独善的な思い込みです。ですが、その確信も目に見えないことを基準としているのです。
高校生のとき、幽霊や霊は存在すると信じている級友がいました。(霊を何度も見た体験や金縛りにもよく遭う話しをしていたので、そういった体験が「絶対にいる」という確信を持たせているのでしょう)ある日、霊体験の話しをすると、クラスメイトに「この科学が主流の現代で、霊とか幽霊なんて存在しないよ」と言われましたが、その級友は「でも霊が存在しないことは科学で証明されていないだろう」と反論していました。
”霊は存在する派”の人は、「存在しないということは証明されていない。だから存在するはずだ」と主張する。”霊は存在しない派”の人は、「存在することが証明されていない。だから存在しない」という。ここでポイントとなるのは、どちらも科学的に証明されていないという同じ条件にも関わらず、それを自分の考えに適合するように解釈し、意見を反する相手には相手にとって不都合な解釈を利用しているということです。
上記の話しは、人の行いとは違う話しですが、人間というのは意見が反する相手に対して、証拠がないという同じ条件にも関わらず自分の方が正しいという確信を持ってしまいやすいという一つの分かりやすい例です。
目に見えないことや数値などで測定できないことというのは、自分が暗黙に正しいと思っていることに都合よく解釈する傾向が強くなりがちです。自分の正しさの基準にも証拠がないのに、相手に証拠がないことをいいことに自分の意見を押し切るのは傲慢な人間になっていってしまう危険性があります。目に見えないことだからこそ、自分の意見や正しさだって確固たる証拠はないと考え、謙虚になることが大事です。そういう謙虚さを持てば、相手を理解しようとする動機にもなるし、自分を立派な人間へと成長させる助けにもなります。