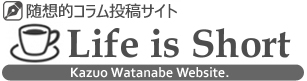2017年度に全国の労働局などに寄せられた職場でのトラブルによる相談は、パワーハラスメント(以下、パワハラと表記)を含む「いじめ」が最多で、6年連続でトップという記事を読みました。その数日後には、長時間労働や職場のいじめ、パワハラなどでうつ病を発症して自殺した元社員の労災が認定されたというニュースが掲載されていました。このようなニュースはもう珍しくなく、度々見かけるものです。
実際、パワハラは世の中で恐ろしほどに野放しになっています。昭和の頃に比べ、体罰などの肉体的暴力や性的いやがらせ(セクハラ)はかなり抑圧されてきています。しかし、パワハラ(特に精神的なダメージを与える行為)はこれらに比べて減っていない印象です。体罰やセクハラは「悪」として分かりやすいですが、パワハラは正義という見せかけの下に実行される分、厄介です。パワハラは、同じ悪でも正義の仮面を被った悪なのです。「仕事」ということに関しては、「責任」「義務」という概念が常に付随し、広義的には「道徳」や「倫理」にも関係しています。仕事に対して厳しいという姿勢は、「正しい」ということを盾に、精神への暴力を正当化しやすいのです。
確かに、中には精神的なプレッシャーがないとダラける人、サボりがちな人、ミスを頻繁に起こす人もいます。その場合はある程度、精神的な圧力をかける必要もあるでしょう。ネガティブな感情を表に出すというのも全て否定されるわけではなく、必要な場面もあるかと思います。ですが、それを意識して人や場合によって使い分けている人(もしくは、言葉や態度などを適切な範囲に制限している人)がどれだけいるかと考えれば、ほとんどいないに等しいのではないでしょうか。
パワハラは、「あなたは間違えているのだから、怒られるのは当然」という状況の正当性を作り上げられて実行されます。ミスをすれば注意をするのは必要なことですが、精神に余計なプレッシャーやダメージを与える必要性はありません。厚生労働省はパワハラを「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義しています。この「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為」がしてはならない制限ですが、「君はミスをしたから叱責される立場にある」という状況の下、「仕事というのは重大な責任感を持つべき」とか「自分は仕事に関して妥協は許さない」などの独りよがりな思い込みが、その制限をあっさり破ってしまうのです。
過剰な叱責は、仕事に対して厳しいという姿勢を全面に出して行われるわけですが、その実、自分より立場や気が弱い人間に対して、ネガティブ感情(特に怒り)を抑制しないで解放させているだけです。人間にとって、高ぶった感情を抑圧することは強いストレスになり、基本的にはしたくないことです。(特に怒りは強い感情です)確かに、怒りや不満のキッカケ(仕事上のミスなど)を作った人がそもそも悪いともいえますが、それでも他人に向ける感情は適切にコントロールされるべきです。ですが、「自分の方が強い立場にあって何故、不満の感情を我慢しなければならないのか。我慢しなくてもよい立場(関係の優位)・状況・理由の全てを成立させれば簡単なことだ。(特に、立場が強ければ理由はどうにでもなる)」パワハラをしている人間は、まるでそう言っているかのようです。
無差別殺人は「無差別」とは言いいますが、被害者は女性や子供などの弱者の比率が高いといいます。酔っ払いが誰かに絡む場合、強そうな人に絡むことはありません。例えアルコールによって理性が麻痺していても、本能的に自分より強そうな相手は避け、弱そうな相手を選択するのです。学校のいじめも、いじめっ子はいじめる対象をランダムにチョイスしているわけではありません。もし理由を求めれば、「あいつはこういうところが悪いから」など、自分の都合のいい解釈で説明すると思いますが、その実は弱い(弱そうに見える)からです。パワハラをする人間もこれらの例と同じです。つまり、パワハラというのは弱者をターゲットにして攻撃する弱い者いじめ以外の何者でもないということです。
パワハラという言葉が定義され、世間に認知されたのは良いことですが、実際はあまり抑制する力にはなっていません。それは「パワハラというのは不当な圧力や言葉の暴力であり、自分の行為は到底、パワハラには当てはまらない」という当事者(加害者)の勝手な思い込みです。(思い込みと言っても意識してそう考えることはなく、無意識にそういう感覚になっている)そして、世の中にあまりに多く、当たり前に存在するので、周囲の人たちにも問題意識が促されないのです。
あなたに精神的ダメージを与える人間は、上司や先輩で立場は上でも、仕事をこなす能力があって社内で評価をされていたとしても、そういうものと人間性は全く別物です。業務上では有能であったとしても、少なくとも人間性はそうではありません。立場の優位性や状況を利用して悪行を実践している卑怯な人間という一面を色濃く持っているということです。そういう人間に対し、私は強い憤りを感じます。同時に思うのは、多くの人間にありがちな「自分は正しい」という思い込みは、他人をそれだけ傷つける行為すら正当化して確信犯にさせる恐さもあるということです。
もし、あなたが弱者の立場にされて被害を受け、日常的に精神的ダメージを負っているのであれば、心から同情します。パワハラがもっと社会的に関心を持たれて、体罰やセクハラのように抑圧されるのは、残念ながら当分先のことになると思います。(この先もずっと状況が変わらない可能性も充分にあります)重要なのは、自己を防御する、自分で自分を守るという考えを持つことです。成す術なくダメージを受け続ける人があまりに多くいるので、心療内科や精神科は常に繁盛しています。目的を持ってやるのとやらないのとでは、成果は大きく異なるものです。